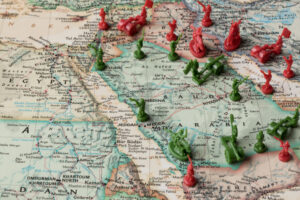プライスアクションの売買シグナルは強力であるがゆえに、それを最初に知った初心者は致命的なミスを犯してしまいがちです。プライスアクションの売買シグナルを本格的に学ぶ前にどんなミスなのか?を知って、あなただけはそのミスを回避しましょう。
プライスアクションの売買シグナルを知った初心者が犯す致命的なミス

売買シグナルとは、FXや株などのトレードをする際、エントリーのトリガー(引き金)となるサインのことです。
FXで勝てない人の特徴としては、移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロス、またはボリンジャーバンドなどのテクニカルインジケーターが発するサインを売買シグナルとして使ってしまうというのがあります。
そういった一般的なテクニカルインジケーターの売買シグナルのほとんどは優位性が全くないことは過去の検証で明らかです。
勝てるFXトレーダーのほとんどは、テクニカルインジケーターではなくプライスアクションの売買シグナルを使ってエントリーします。生のローソク足1本~数本で形成されるローソク足のパターンをエントリーのトリガーとします。
では、プライスアクションのシグナルを使えば即勝てるのか?
残念ながらそう甘くはありません。
僕が使っているプライスアクションの売買シグナルについて解説する前に、とても重要な注意点を解説させてください。
これを知らないと、大変なことになってしまうので、最初のうちに解説しておきます。
それは何かというと、ズバリ
プライスアクションの売買シグナル単体では、大した優位性は無い
ということです。
プライスアクションの売買シグナルは、上位足のトレンド分析やレジサポ分析などが終わったあと、最後のゴーサインを出してくれるツールとして使う場合にのみものすごい優位性を発揮してくれます。
以前、全通貨ペアを対象としていくつかのプライスアクション売買シグナルのバックテストを実施しました。その時に分かったことは、プライスアクションシグナル単体ではたいしてもうからないということでした。多少プラスにはなりましたが、安定して右肩上がりに勝てるようなものであはありませんでした。
プライスアクションの売買シグナルを覚えた人がまずやってしまう致命的なミスというのは、チャート上に現れたピンバーや含み線などの売買シグナルを使って片っ端からエントリーしようとしてしまうことです。
片っ端からエントリーしてもたいして勝てないので、あなたは絶対にそんなことをやらないようにしてください。
じゃ、上位足の環境認識と組み合わせたらいいんでしょ?
と思いますよね。
でも、順番が大切です。
上位足を使った環境認識やトレンド分析 → 最後にプライスアクションの売買シグナル というのが正しい順番です。
最初にプライスアクションの売買シグナルを探し、その後にじつけで上位足の環境認識をしてはダメです。
よく、プライスアクションの売買シグナルを検出してアラートを出してくれるインジケーターがありますよね?
そういったインジケーターを使って売買シグナルを検出し、後から上位足の環境認識を無理やりやって、エントリーを正当化しようとしてしまっては勝てないんです。
環境認識やレジサポの分析はかなり主観的なものです。ですから、完璧な形のピンバーや含み線が出た!という事実に興奮してしまうと、環境認識やトレンド分析の精度が鈍ってしまうんですね。
ですから、くれぐれも、プライスアクションの売買シグナルを最初に探すようなことはしないようにしましょう。
プライスアクションの売買シグナルは、最後の最後に使う、と覚えておいてください。